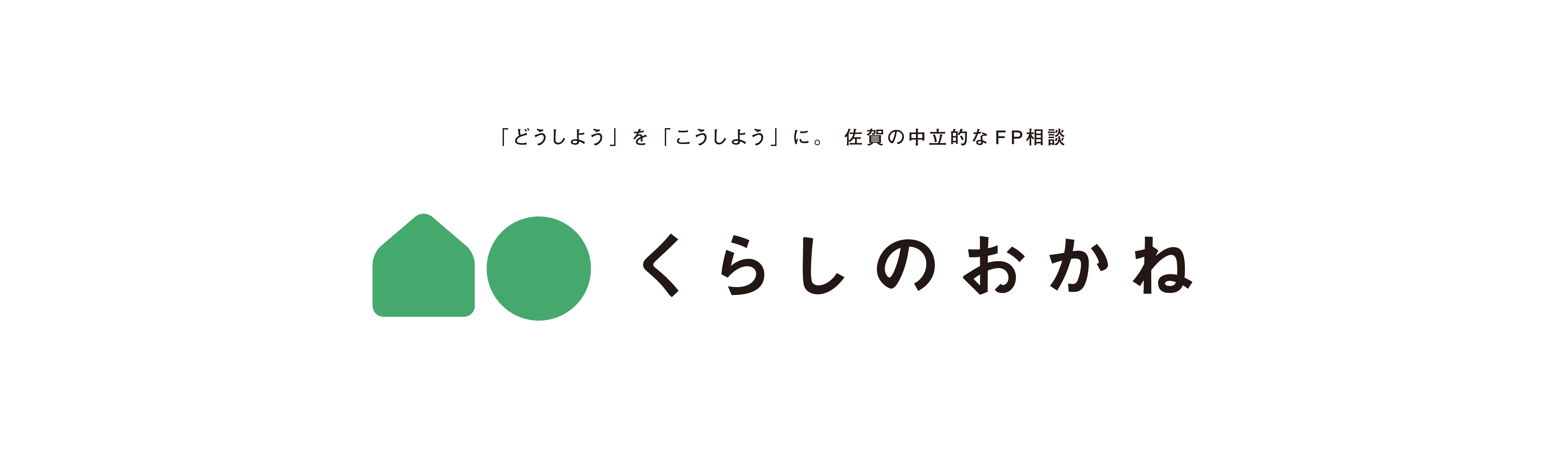制度の改悪続きで雲行きが怪しいと思われている「年金」
わたしも「よく知らない」時は、自分が老後をむかえるときはどうなるのだろうと不安でいっぱいでした。
メディアでは
「年金制度は破綻する」
「年金の受け取り年齢を後に後にされていく」
と不安を煽る表現が目立ちます。
でもFPの勉強を始め、自分から調べてみると破綻するとはとても思えない。
破綻しないように、あの手この手で制度の見直しがされている。
ということが分かりました。
そもそもの制度の保障が手厚すぎて、それを修正しているから「改悪」しているように見えるだけ。
今の日本経済は低成長、かつ深刻な少子高齢化が問題で、この仕組み自体を見直さないといけなくなっています。
時代と共に変化するのは自然なこと。
なんでもかんでも、今まで通りなわけはないので、そういった変化を受け入れて自分にできることを冷静に考えることが大切なんだろうと思います。
本当の問題は今までがこれからも続くだろう前提で、国の制度を手厚くしすぎたことではないかと推測しています。
そのために今、国が行っている対策の一部を紹介します。
国の対策
1.働き手を増やす
年金は現役世代が保険料を支払い、それを財源として高齢世代に年金を給付する「世代間扶養」の仕組みです。若者から高齢者へ仕送りしているイメージが分かりやすいかもしれません。
なので払う人ともらう人のバランスがポイントです。
今現在は共働きがあたりまえになり、60歳の定年が65歳になり、さらに高齢期に入っても仕事をする人が増えています。
そこを加味すると「働く人」の人口はほとんど減っていません。
ただ「働く人」の中で「社会保険料」を払う人が増えないと「年金制度」のプラス要因にはなりません。
なので政府はパートでも社会保険に入れるように、加入基準の緩和をじわじわと進めているところです。
「支払いが増える」ことに抵抗がある人もいますが、メリットもちゃんとあります。
○自分の年金額が増える
○傷病手当、障害年金が手厚くなる
仮に腰痛が悪化して仕事に行けなくても、お医者さんの「自宅療養」の診断がもらえれば給与の手取り額の8割近くが傷病手当(非課税で)としてもらえることになります。
そして健康保険上の扶養から外れると、上限を気にすることなく働けるので、収入が増やせるのが一番のメリットではないでしょうか。
2.運用している
年金の中には「積立金」としてプールされているお金があります。
2001年より厚生労働大臣から寄託を受けた「GPIF]が市場運用をスタート。
国内の株式と債券、国外の株式と債券をそれぞれ25%づつの、リスクを抑えたポートフォリオで運用されています。
GPIFの役割や運用実績のチェックはこちら。
2023年9月時点の累積収益は約126兆円(もうけ部分だけ!)。
平均収益率は3.9%。
100年の財政計画の中で、将来の不足分を補うためです。
この積立金からまかなわれるのは1割ほどになります。
3.受け取る年齢を選べるようになっている
基本的には65歳に受け取るものになっていますが、60歳から75歳の間で受け取り開始年齢を選べるようになっています。
繰り上げると受け取る金額は減ってしまいますが、後ろに繰り下げると下げた分だけ増える仕組みになっています。
今の60歳、65歳の人は昔に比べると若々しく、元気な人が多くなっています。
元気なうちは働いて、年金を受け取るのは少し待っておく。
働くのをやめたときに増えた年金を、死ぬまで受け取り続けることができるようになっているのがこの仕組みです。
その人の「現状」に合わせて選べるのは親切な設計だと思います。
結論・年金制度は破綻しない
2004年の時点で少子高齢化が年金に与える影響についてはしっかり議論がなされています。
改悪はされても、老後生活の主軸は年金です。
仮にもらえる金額が2~3割減ったとしても大丈夫なくらいに、自分で資産形成しておくとちょど良いかと思います。
どういうデザインにすると多くの人を守れるのか。
そのための制度の見直しに過剰に嫌悪感を感じないようにしたいですね。
メディアの煽るような見出しに踊らされることなく、冷静に考えてもらえたらと思います。