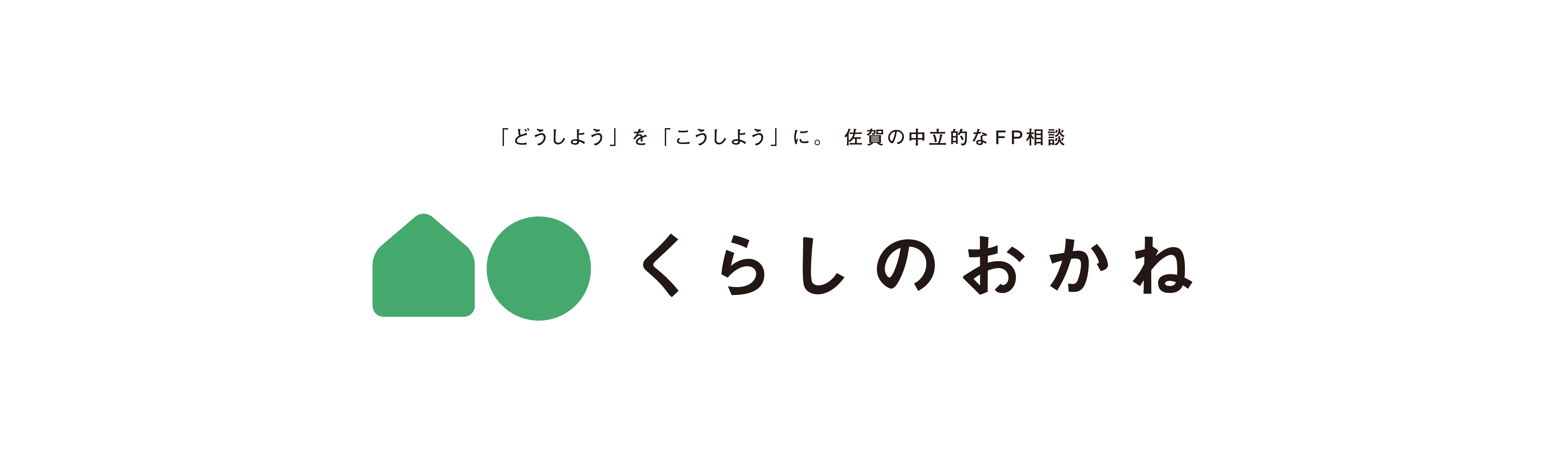前回、税金の扶養の話を書きましたが、配偶者以外の扶養も参考までに。
労働を増やさず、手元にお金を残すことができる「所得控除」、頑張って勉強していきましょう!
お子さんが大学生の年齢(19歳~22歳)の場合は特に注意が必要です。
ちなみに、「学生であるか」は問題ではなく年齢がポイントなので、社会人になっても所得が少なかったり、安定しないお子さんも対象になるかもしれません。
「特定扶養親族」(19歳~22歳)の子どもの年収が103万円を1円でも(!!)超えると、親は扶養控除を受けられなくなり、所得税控除分63万円と住民税控除分45万円が新たに課税対象となります。
親の所得金額(年収から各種控除を引いた後の額)が
195万円超~330万円以下の所得税率は10%
330万円超〜695万円以下の所得税率は20%
住民税率は一律10%です。
親の所得税率
10%なら(63万円×10%)+(45万円×10%)=10万8,000円の負担増
20%なら(63万円×20%)+(45万円×10%)=17万1,000円の負担増
これをみると「ひゃ~~!103万円に抑えてもらわなきゃ!」となるかと思いますが、これも個別案件で事情が異なります。
冷静な判断が必要なのはこのパターン。
① 住宅ローン控除の金額が大きく、所得税の支払いがなく、住民税もふるさと納税等で上手にコントロールされている場合。
② 子供本人がお金が必要な場合。
この場合は103万円を超えていくら稼いだかと、この控除がなくなっていくらの税金が増えてしまったのかを比較するといいかもしれません。
所得税率10%の親なら、子供は10万円を余計に働いて稼ぐより、103万に抑えてもらって10万円を親から子に渡した方が学業に専念できて、いいかもしれません。
よく確認されることをおススメします。
扶養している人が1人減って所得が増えるということは
なんらかの「所得制限」がある制度を使っている場合、
この大きな控除を失うと、所得制限に引っかかる可能性も出てきます。
例えば大学無償化や高校無償化などです。
上の子が特定扶養でなくなったことで下の子の無償化が使えなくなるなんてことも起こりえます。
そうなると、親の税金が増えただけでは済まないぐらいの負担を負う可能性も…。
厳重注意です。
扶養控除はあと2つの分類があるので、そちらも参考までに。
①一般の扶養
16歳~18歳or24歳~69歳
控除額38万円
(住民税は35万円)
②老人扶養
70歳以上
控除額48万円・同居だと58万円
(住民税は38万円・45万円)
そしてこの2つにまたがる65歳以上の公的年金を受け取っている親の所得は給与所得控除と別の公的年金の控除があるので、年金だけの収入なら158万円までの親はこの扶養の対象になります。
(国税庁のホームページに公的年金控除額の一覧がありますので、気になる人はそちらもぜひ。)
ちなみに扶養対象親族が障害者の場合は障害者控除も合わせて使えますのでお忘れなく。
ややこしいですね~~~。
税金の仕組みは本当に難解です…。
でもなんでこんなに複雑かと考えてみると、養う家族が多かったら大変だから、なんとか税負担を軽くしようとする国のやさしさ…。
だからある程度は仕方ないということにしておきましょう。
やさしさをちゃんと受け取れるよう、発信を続けていきたいと思います。