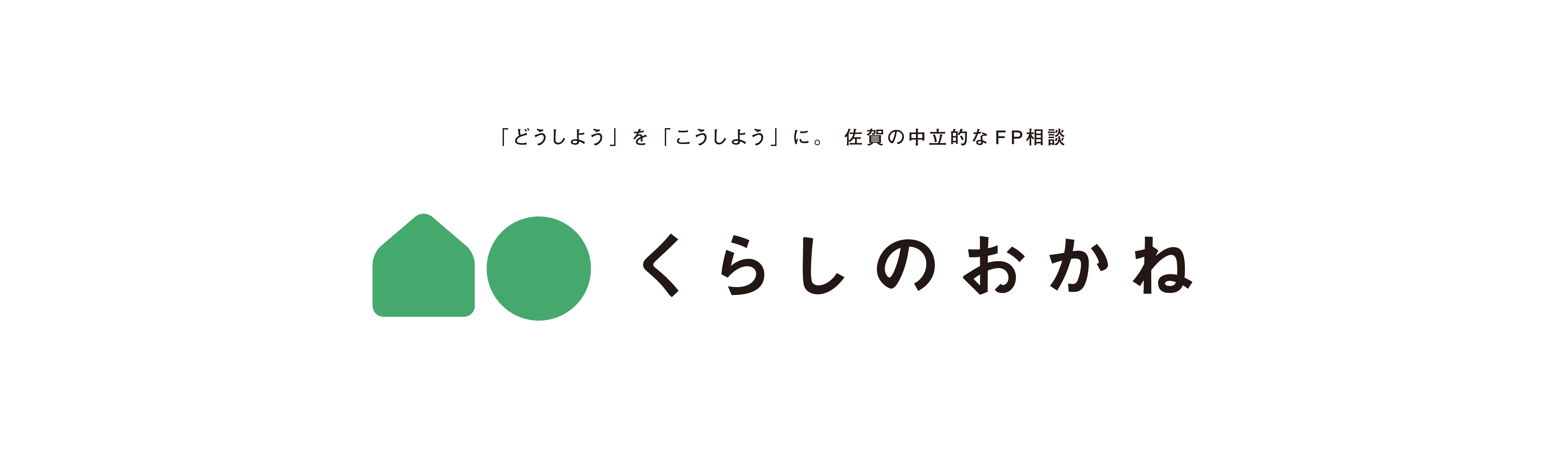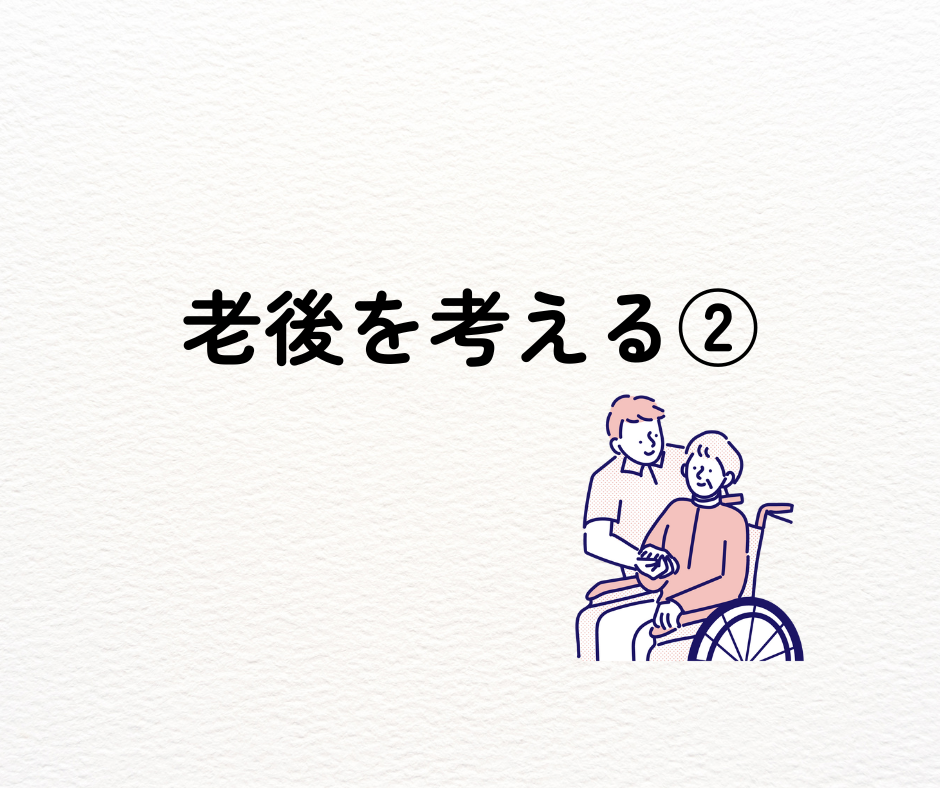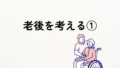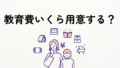結局じゃあいくら必要なのか、見積もりの手順を追ってみましょう。
① 不足する金額を計算する。
一年間で受け取れる年金から年間の予想される生活費を差し引き、それに年金受給開始年齢から平均寿命の年数をかける。
② 老後の特別支出の予算立て。
住宅リフォーム、葬儀費用、子供への援助、レジャー費など。
③ 介護費用の見積もり。
ここの概算を出すのがとてもむずかしいですよね。
子育て世帯にとってはまだまだ先の話ですから、いずれにしても正確に計算することはできません。
ですが、とりあえずのこのくらいの金額を出すことによって「今やるべきこと」が見えてきます。
R3の全国の実態調査の平均自己負担額は1人当たり580万円とのこと。
一時費用は74万円、月々の支払いは8.3万円が5年間かかるという計算です。
これは在宅も施設入所も合わせて出された平均値です。
この平均値から夫婦2人で少なくても1,000万円は貯めておかないと!!
とマネーセミナーの講師はおっしゃいます。
介護認定を15年前に受けた母を持つ私からすると、平均値は中央値ではなさそうだな・・・ということ。
こういうデータの平均値は大きい数字に引っ張られますので冷静に見る必要があります。
支給限度額の1割負担の範囲内でうちの母はやりくりしているので、要介護1の区分の毎月の自己負担は2万円ほど。
もし一人暮らしだと、ヘルパーさんの回数を増やしたりと増額になりそうですが、弟が同居してくれているのでこのくらいで済んでいます。
一時費用も玄関のスロープ、お風呂の手すり、ポータブルトイレ、ベットくらいでしたね。
20万円を上限に9割の補助があるので、18万円までは申請した後に戻ってきます。
医療・介護費の自己負担額は所得によって1~3割の負担割合があること。
医療・介護費が高額になった場合は年間の上限があること。(詳細は前回の投稿で)などから、もし介護度が重くなってしまった場合の費用のある程度の予想ができます。
老後の年金の受給予定額で自分の自己負担割合と年間の上限額も分かりますので、そのシュミレーションを一度するとイメージがしやすいかと思います。
ケアマネージャーさんによく相談して支給限度額の範囲でプランニングしてもらう。
所得が大きくて、しっかり準備しておきたい人はそれなりの金額で見積もればいいのです。
介護度が重くなってしまい負担が重くなれば、同居している子供世帯と住民票上だけの世帯分離をするなどで支払いを減らすこともできます(ちゃんと仕組みを理解した上で、ですが)。
なのでこれを踏まえて自分の場合はどのくらいを見積もろうかと、自分の頭で考えることが大切です。
平均的な所得の人なら夫婦2人で介護費1,000万円は十分な見積もりだと私は考えています。
※厚生労働省のホームページより引用・居宅サービス利用時の、利用できるサービスの量(支給限度額)の要介護度別の上限。
この1割~3割を負担。(1ヶ月あたりの限度額)
以上の①②③をすべて足したものが老後までに必要な資金ということです。
そしてお金よりも大事なのは、困ったときにサポートしてくれる家族・友人関係を築いておくことです。
私たちが老後を迎えるころにケアをしてくれる人がどれほどいてくれるでしょうか。
今でも介護業界はなり手不足が問題で、日本の賃金の上昇率が低いことから、海外からのなり手も減ってきています。
お金があってもケアしてくれる「人」がいなければ意味がありません。
日々の人間関係を良好にしておくこともとても大切なことだと思います。