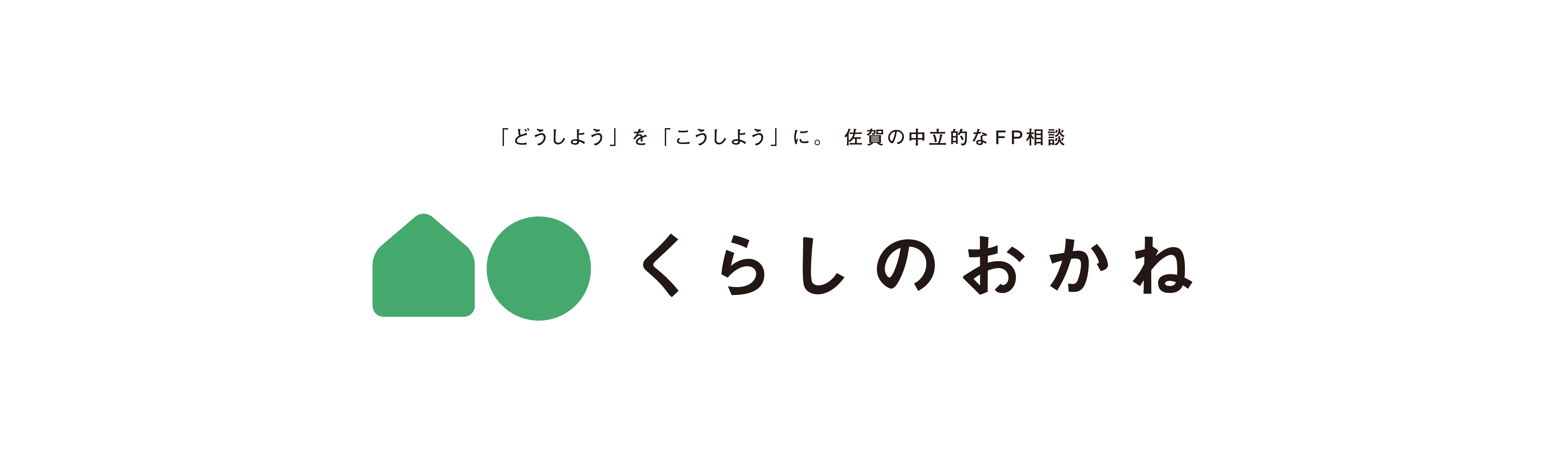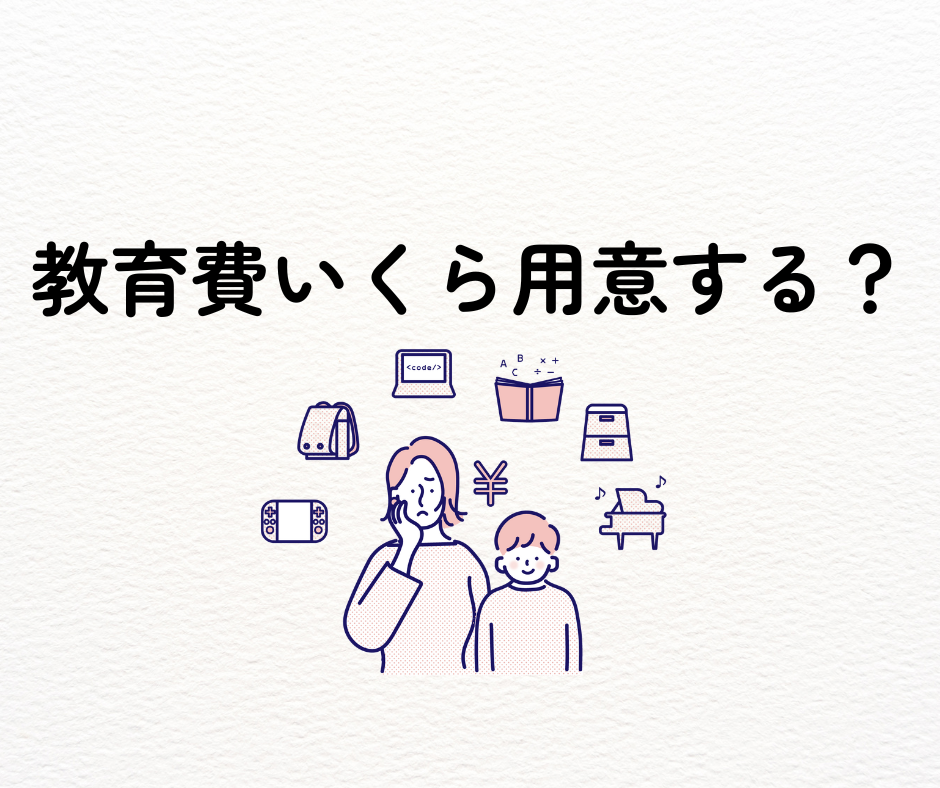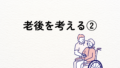子育てママさんの気になる費用の一つ、教育費について。
① いつまでにいくら用意すればいいの??
基本的に公立を選択するのであれば、学校教育費は幼保は満3歳以上は保育料は無償化となり、給食費などで月8,000円、小学校は月9,000円、中学校は月15,000円程度が平均的な金額になります。
これに習い事や部活動などを足すと2倍ほどの金額が平均値として出てきますが、あくまで平均値です。
各家庭の事情によって出せる範囲内でやればよいと思います。
2010年から始まった高校無償化は親の所得制限があるものの、対象になれば恩恵は大きいですね。
(年収目安は910万円程との記事も見かけますが、実際は所得控除の金額や子供の数で変わるので、年収1000万を超えても対象になる場合もあります。判定ギリギリの人は一度計算方法を確認しておくことお薦めします)
無償化と言っても、教材費・制服代・通学交通費・部活動費・大学受験のための塾代などはかかるので、油断しすぎないようにしましょう。
ここまでは家計のやりくりで何とかなるものですが、問題はここからです。
国公立大学の文系の教育費だけなら300万円ほどという記事も見かけますが、これには注意が必要です。
入学前にかかる他の大学の受験料・滑り止めの大学の入学金・教科書代・納入金・通学費用などは含まれません。
これらを含めると500万円程必要だと言われています。
(私立文系で700万・私立理系で800万)
さらに県外の大学などで自宅外通学になると生活費の仕送りまで必要になってきます。
子供が小さいとどういう進路になるか予測が難しいですが、とりあえずで教育費のゴール設定を仮決めし、後から微調整するのがベターだと思います。
② どうやって貯めたらいいの??
ひと世代前でしたら学資保険と貯蓄という選択肢が一般的だったと思いますが、今は超低金利の時代。
15年かけても3%、ならまだいい方かもしれません。
かけた金額より少なく返ってくる学資保険も存在します。
おススメは児童手当(200万ほど)を貯金しておき、子供が生まれたばかりで期間が取れる人は5年ほど積み立て投資をしてから、6年目以降は貯金というスタイル。
月々の積み立て投資・貯金を14,000円を18年間。
積み立て投資の年利を3%での運用を想定し試算をすると350万ほどになります。
児童手当と合わせると550万円になりますので自宅から国公立大に通う分には足りる計算になります。
もし一人暮らしをするようになったら、貯めたお金を仕送り費用にして学費は奨学金を借りてもらうことも選択肢の一つです。
2024年からの新NISAをフル活用したい気持ちになるところですが、教育費は使う時期が決まっているものなので、そのタイミングで暴落していたら目も当てられません。
15年以上の投資期間を取ることができればマイナスにはならないと言われていますが、あくまでも過去のデータからの参照です。
適正なリスクを取りましょう。
③ 奨学金
今は超低金利の時代で、2人に1人は奨学金を借りているくらい一般的になってきました。
親に現預金があってもあえて子供に奨学金を借りてもらい、なるべく運用に回して増やしつつ、返済のタイミングで子供に渡す裏ワザ的な考え方もアリだと思います。
2023年3月の奨学金の返済金利は0.905%。
3%の金利上限があるので、運用の利率がそれ以上であれば悪くはない話です。
この時の注意点は贈与税が発生するかもしれないということ。
奨学金は子供が借りた借金という扱いなので、親が返済を手伝うと親から子へ贈与があったものとみられます。
年間110万円以内であれば非課税ですが、それを超えると10%~金額に応じて贈与税が発生します。
子の借金返済なので、教育資金の一括贈与の非課税制度(1500万まで非課税)を使うことはできません。
ちなみに奨学金の平均借入額は324万円、毎月1.6万円を15年かけて返済するイメージです。
あとチェックしておきたいのが民間企業の奨学金。
企業が公益財団法人を立ち上げて、返済不要の給付型奨学金を行っているところもあります。
ダイソーやニトリ、電通など。
「奨学金.net」で調べてみてください。
親と子の負担が偏らないように、進路を決める際にはしっかり話し合う時間をとり、後悔のない選択をしたいですね。