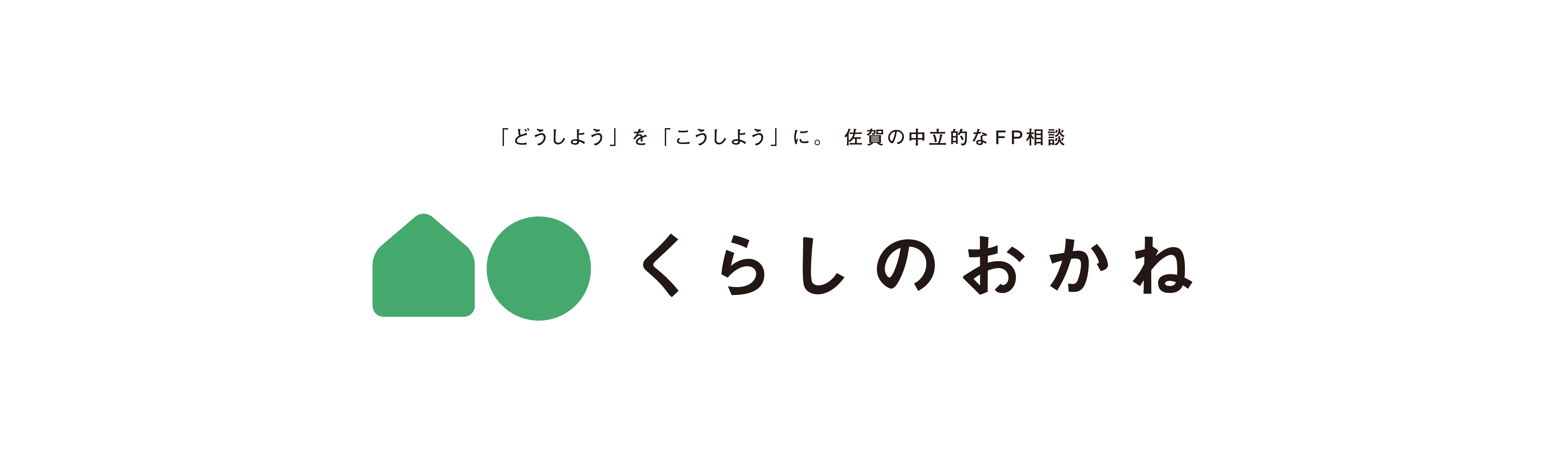ママの働き方について。
前回、健康保険上の扶養について書きましたので、今回は税金上の扶養についてです。
税金の扶養というのは、簡単に言うと「妻を養っているので税金を安くしてください」と、養っている側(夫)の税金の計算上有利にできる制度です。
もともと配偶者の扶養控除は年収「103万円」まででしたが、2018年にこの配偶者の扶養のルールが改正されました。
103万円を超えても150万円までは一律38万円の控除が受けられるようになったのです。
これはとてもありがたかったですね。
こちらもややこしいところがあるのでチェックしておきましょう。
1・妻の所得制限
配偶者控除は所得48万円以下、配偶者特別控除は133万円以下であることが要件です。
ここでのポイントは、「年収」ではなく「所得」ということです。
所得というのは簡単に言うと「もうけ」の部分のことを言います。
給与の場合は給与所得控除(仕事のためのみなし経費のようなもの)を引いた額が所得になります。
年収103万円の人は給与所得控除55万円なので所得が48万円になります。
(※国税庁のホームページに年収ごとの計算方法の説明があります。)
夫の年収が1,000万円を超える場合は、配偶者の所得控除はありません。
2・「扶養」の考え方の注意点
年収103万円~150万円の幅内の控除額は一律38万円ですが、150万円~201万円の幅は段階的に金額が減り、それ以上は控除対象から外れます。
103万円までが完全扶養の配偶者控除でそれ以上が配偶者特別控除となります。
児童手当や高校授業料無償化、住民税の非課税などの判定のための所得制限は「扶養の人数」によって上限額が変わります。
この扶養にカウントできる配偶者は年収103万円以下になるので、該当するかしないかで判定が変わるような人は注意が必要です。
3・ 投資の利益と扶養の関係
例えば「特定口座・源泉徴収なし」を選択した場合で株式を売却し、年間のトータルで利益(もうけ)が50万円出た場合は税金の扶養を外れてしまいます。
主婦で無職であったり扶養内パートであったとしても、これらの確定申告が必要な口座でのもうけは税金の扶養に影響することに注意しましょう。
(厳密にいえば、所得税率の一番低い5%の人なら、住民税と合わせても15%になるので源泉徴収の20%で終わるより、確定申告をした方が5%の節税にはなります。)
扶養を外れたくないときは確定申告をせずに税金の精算を完結させればよいわけですから、NISAの口座でするか、「特定口座・源泉徴収あり」を選択すると所得にカウントされないので安心です。
iDeCoは運用益は非課税ですが、受け取り方はちょっと複雑です。
60歳以降の受け取り方によっては扶養を外れる場合もあるのでなんとも言えないところです。
4・夫の給与に家族手当がある場合の基準も確認
夫の給与に家族の扶養手当がある場合は基準と金額をチェックしましょう❕
(税金ではないですが)
もし判定基準で年間12万の家族手当が出る場合は115万円分働いても世帯の手取りは103万円の時と同じということです。
12万円分働いたのに・・・です。
これなら103万円までに抑えた方が、一か月分くらいの自分の時間が確保でき、精神的にも安全かもしれません。
以上と前回の社会保険の内容と総合的に判断して、自分にとってちょうどいい働き方のヒントになればうれしいです。